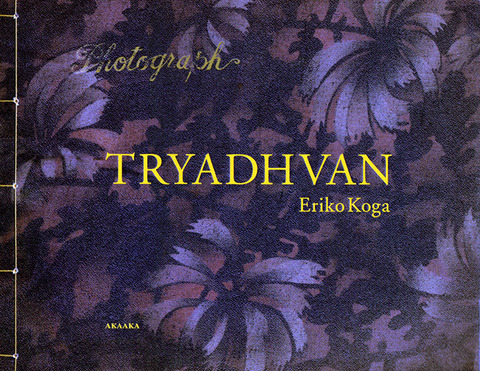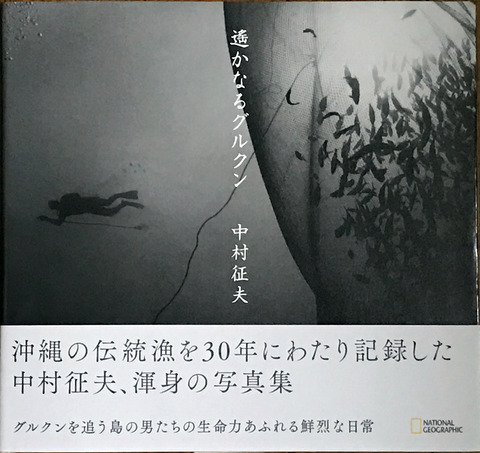あまり過剰反応しては良くないけれど、2017年の世界情勢は、お正月から不穏な状況を醸し出している。イギリスのEU(European Unionヨーロッパ連合)離脱をはじめとするヨーロッパの情勢は混沌としているし、世界的なISのテロ活動もあるが、なんと言ってもその原因は、アメリカのトランプ大統領の発言と行動に代表されるだろう。先人の英知がなんとか築いてきた世界情勢のバランスを、日本流に言えば、あたかもちゃぶ台をひっくり返すような勢いである。あらゆる面で狭くなった地球上で、「共生」ではなく「対立」をあおるようなナショナリズムは、未来への希望を閉ざすことにほかならない。
写真分野においては昨年、すぐれたアーカイブに基づく特に海外写真家の素晴らしい写真展が目立ったが、今年は日本の先達ともいうべき写真家の作品をもっともっと観る機会を増やして、知られざる先人の秀作にお目にかかりたいものである。

石原悦郎とツァイト・フォトを描くことで1978~2016年の写真史の一翼を表す
粟生田 弓『写真をアートにした男 石原悦郎とツァイト・フォト・サロン』
(2016年10月、定価2,200円+税、小学館)
私は昨年3月2日のfacebookに、石原悦郎*の葬儀の一報を受けて次のようなコメントを投稿した。「ツァイト・フォト・サロンのオーナーである石原悦郎さんが2016年2月27日、肝不全で亡くなられました。享年74歳でした。私にとって思い出深いのは、1978年知り合いの写真家の紹介で銀座のカフェで最初にお目にかかったときの印象です。当時、美術畑で活躍されていた石原さんでしたが、会うなり『これからは写真だ、日本橋三越前に写真のギャラリーを開設するのでよろしく』という主旨の話を情熱的に話されたことでした。ギャラリー開設当初は、海外ではマン・レイ、ブラッサイ、国内では木村伊兵衛、植田正治、桑原甲子雄など、故人や大御所のファイン・プリントが並びましたが、そのうちつぎの時代を担う森山大道、荒木経惟、北井一夫さんをはじめ、安齊重男、石内都、杉浦邦恵、井津建郎、柴田敏雄、畠山直哉、オノデラユキ、鷹野隆大、尾仲浩二、楢橋朝子、佐藤時啓さんなど若手写真家へと移って行き、併せて新鋭の写真評論家であった故・平木収、飯沢耕太郎、金子隆一さんなどとも積極的に付き合われ、国内屈指の注目の写真ギャラリーへと発展させました。美術はもちろんのこと、クラシック音楽やさまざまなクリエーティブ分野に造詣が深く、その豊かな知性と感性に基づく眼力の鋭さにより、写真の未来を常に模索されていたように思われます。ご冥福をお祈り申し上げます。」というものであった。正確には後述する図録『ZEIT-FOTO SALON 1978-2016』を見ると、オープン当初に展示された日本人写真家は最初が小泉定弘、つづいて北井一夫であった。
本書の著者である粟生田弓**の「追悼・石原悦郎さん──あとがきにかえて」の冒頭によれば、「本書は、長年石原さんの右腕としてツァイト・フォトを支えてこられた鈴木利佳さんより、『石原さんの本をつくりたい』とお話を受けたことにはじまりました。おおよそ4年ほど前からインタビューを開始し、この1、2年間は毎週土曜日に石原さんとの対話の時間をもたせていただきました。在籍していたのは2006年から2008年という短い期間ではありましたが、じつは私も元スタッフで、知り合ってからちょうど10年が経ちます。」とあるように、著者の石原への取材は長期間におよび、その内容は──「石原悦郎の生い立ち」にはじまり、画廊時代、日本で最初の写真画廊ツァイト・フォト・サロンの開設、「つくば写真美術館」の設立と失敗、再チャレンジ、「写真家たちとつくる新しい写真」への情熱、「コレクションに託された未来」──にわたり克明に書き起こされ、そこには石原とツァイト・フォト・サロンの情熱に惹き寄せられた多くの写真家、評論家、写真および美術関係者の名前が飛び交い、1978~2016年の写真史の一端が記録されている。第5章「つくば写真美術館の夢と現実」には石原自らが手書きで綴った「筑波写真美術館(仮)設立趣旨」なる草稿原稿(A4レポート用紙7枚)からの一部が登場するが、その文章には『核心は写真家個々の知的な問題意識が独創的形式でしっかりと表現されているか否かということに尽きます』とある。これはまさに石原とツァイト・フォト・サロンの写真に対するポリシーである。
親子以上に年の差のある粟生田と石原だが、いわば本書は二人の合作と言えよう。写真史にとって一翼を表すと記したが、その比重は、数パーセントどころではないことを留めておこう。
併せて昨年9月から年末にかけて3回「友人作家が集う-石原悦郎追悼展」が開催され、同時にこれまでツァイト・フォト・サロンと姉妹ギャラリーイル・テンポ(il tempo)で開催された全展覧会の案内はがきが掲載された図録『ZEIT-FOTO SALON 1978-2016』(2016年9月、定価1,500円(税込)、ZEIT-FOTO SALON)が刊行されたことを報告しておこう。
*石原悦郎(いしはら えつろう):1941年東京都生まれ。立教大学法学部卒。卒業後欧州に遊学、フランスの古典芸術に魅せられる。ギャルリー・ムカイ、自由が丘画廊を経て独立。1978年に東京・日本橋室町に日本で最初のコマーシャル・フォト・ギャラリーであるZEIT-FOTO SALONを創設。フランス、アメリカをはじめとする海外作家の紹介や日本人作家の発掘に尽力し、日本に「オリジナル・プリント」という考え方を広める。2000年代に入ると中国や韓国といったアジア圏で自身のコレクション展を企画し、大きな影響を与えた。また、絵画やワイマール期のSPレコードの収集家としても知られる。2016年2月27日、肝不全により亡くなる。
**粟生田 弓(あおた ゆみ):1980年東京都生まれ。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。メディア論を学ぶ。在学中にツァイト・フォトのスタッフとなり、画廊のプレス・リリースや展覧会用カタログなど執筆に関わり、その後独立。2010年ファッション・ブランドRIVORAを立ち上げ現在に至る。編著に『1985/写真がアートになったとき』(青弓社、2014)
〈以上、『写真をアートにした男』より一部アレンジし抜粋させていただいた〉
つぎに紹介するのは、ツァイト・フォト・サロン開設当初から最後まで石原悦郎と行動を共にした北井一夫のエッセイ集である。
実直でオープンな写真家のエッセイ集
『写真家の記憶の抽斗 北井一夫』
(2017年1月、定価1,600円+税、日本カメラ社)
北井一夫(1944-)は言わずと知れた第1回(1975年度)木村伊兵衛写真賞受賞者である。私の中では横須賀の原子力潜水艦寄港反対闘争をテーマとした写真集『抵抗』や『アサヒカメラ』における新東京国際空港反対闘争『三里塚』、そして受賞作『村へ』という作品からドキュメンタリー写真家の印象が強く、アート主体のツァイト・フォト・サロンとは結び付かなかったのだが、石原とはツァイトオープン前の1977年からの付き合いだそうで、早くも79年1月の「浦安」の写真展から登場している。
このエッセイ集の表題「抽斗」は「ひきだし」と読む。2014年5月から2年間『週間読書人』に「記憶の抽斗」として連載された600字のエッセイ100編をまとめたものである。ある写真家に言わせると北井一夫ほど実直でオープンな写真家はいない、と聞いていたが、本書を読むとそれがよく分かる。特に「夕暮銚子」(「いつか見た風景」)に登場する荒木経惟とのやりとりは短文ながら二人の性格がとても象徴的に表されていて思わず吹き出してしまう。全編にわたって写真にまつわるエッセンスが詰まっている。
裸身と化した花のきらめきを写し止める
吉田昭二写真集『TRANSPARENCY』
(2017年1月、定価3,000円+税、日本カメラ社)
作者はあとがきに「花の仮の姿を捉えるのは・・・ 動きの中の一瞬と、光と、目線が重なった時である」と記している。それで思い出されるのは、かつて(2002年7月から)銀座ニコンサロンで開催された公開講座に登場した宗教学者で哲学者の中沢新一の講演である。紹介されたのは土門拳の撮影エピソード。鎌倉東慶寺の仏像撮影の現場に出くわしたときのことだ。車椅子でカメラを構え助手に指示していたという。「突然助手に向かって『ここだ!』というのです。その時僕は『ここ』の意味がわからなかったのですが、その後、土門拳の助手をしていた写真家の篠山紀信と話をした時に、こんな話を聞きました。──僕はカメラのセッティングをして何時間も構えているのですが、横に座っている土門さんが突然『今だ、篠山君。仏像が走った』と言うのです。その『仏像が走った』瞬間にシャッターを押さないといけないんです──と。あの人の写真は仏像が走り出す瞬間を撮るんだと言いました。」「こういう写真を見て私たちは非常に驚きます。私たちの目や認識、記憶では、写真の写すこの一瞬を捉えることができないからです。カメラが短時間にスライスした現実を私たちは写真で見ますが、私たちの認識はこの光景を『そのもの』としか捉えません。写真とは、私たちの認識の中のすっぽり空いた穴や瞬間を捉えることができるメディアなのだと思います。」という鋭い指摘であった。
吉田の花の写真は、まさに水中を漂いながら見せる花の一瞬の輝きを見事に捉えている。その透明感漂う花は、写真集『花たち』(1990年)から近年の『花化粧』『花宇宙』『Beat 2』(2003~2012年)まで、花の美を、独自の手法で追い求めてきたからできた技に違いない。
「日々平々凡々」の「一瞬の輝き」を表す
小池英文写真展&写真集『瀬戸内家族』
(2017年1月14日~1月23日、コニカミノルタプラザギャラリーC/2017年1月、定価3,300円+税、冬青社)
コニカミノルタプラザの最後を飾るにふさわしい写真展であった。昨年銀座ニコンサロンで開催された広島の藤岡亜弥写真展「川はゆく広島」や山口の下瀬信雄「つきをゆびさすII」、あるいはまたもっと端的には、このコニカミノルタの同じ会場で2015年に展示された沖縄の鳩間島と西表島の船浮集落を取材した山下恒夫「続 島想い shimaumui continued」の“瀬戸内版”といえるような作品である。日々平々凡々と生活し生きることがどれほど貴重なことかを、これまた平々凡々に表す写真の何とすがすがしいことかを示している。しかし、この「平々凡々」を表すのは思っているほど簡単ではない。いや、とてもむつかしい。前述の吉田昭二の花の作品と同じように、あるいはまた中沢新一が指摘したように“特技”とも言える「瞬間を捉える」のが写真であるからだ。平々凡々とシャッターを切っても求める瞬間は写らない。小池英文の1点1点にはやはり、「一瞬の輝き」が見事に写し止められているのだ。
入り混じる混沌とした過去・現在・未来
古賀絵里子写真集『tryadhvan』
(2016年10月、定価6,000円+税、赤々舎)
当たり前のことではあるけれど、誰しもこの世の中には知っていることよりも、知らないことのほうがはるかに多い。古賀絵里子は前作のカラー作品集『一山』から新境地に入り、この作品では寺に嫁いで子供を産み、またさらなる新境地に入ったようである。ここには、いまを精一杯に生きる古賀絵里子の日常における多くの想いが、まるで走馬燈を見るかのようにつぎつぎと、モノクロームの映像で展開する。その有様は、昨年の写真展(エモン・フォトギャラリー)での構成よりはるかに進化したものとなっていて、その変幻自在ともいえる構成力が素晴らしい。巻末の竹内万里子の解説には、「本書のタイトルである『Tryadhvan(トリャドヴァン)』とは、サンスクリット語で過去世・現在世・未来世を指す『三世』を表す仏教語」とあった。